
本日もメルマガの共有です。
先週登壇していました、PDCA研修で感じたことです。
業務を効果的に回すPDCAサイクルはご存知の方が多いと思いま
(効果的な回し方はまた今度ゆっくりと・・・)
でも、場合によってはPDCAのPから始めない方が良いケースも
私は良く「C」から始めています。
敢えてPDCAの言葉を使うなら、
C⇒D⇒C⇒A⇒P⇒D⇒C⇒A
みたいな感じ。
と言うのも、緻密なPを考える時間がない時とか、やってみて考え
例えば採用活動とかはPDCAが効果的だと思っています。
目標設定をし、行動計画を作り、進捗確認の指標を決め、やってみ
ただ、キチンとPしておかないと無駄なDになるかもしれない。
勿論CとAで修正はしますが、でも、採用活動は結構な金額を投資
だからしっかりと「P」します。
でも、例えば業務改善とか。
これはやってみて走りながら考える方が良い。
スピード感もそうですし、先に「C」(現状把握と仮説を立てる)
で、また検証して修正する。(「C」と「A」)
そこで初めて再プラン。
この方が早いし効果的だと思います。
このサイクルを「OODAループ」と言うそうです。
Observe(観察)⇒Orient(仮説)⇒Decide(
実は私は昔コンサル会社にいた時の上司に「森川君はPが弱いな~
その自覚はあります。すぐにDoしたくなるのです。
当時の私のまずかったのは、Dの後のCも適当だったこと。
いわば、D、D、D、Dなのです。Dしかない。
だから活動のレベルが中々上がりませんでした。
CとAがあれば多分そんなこと上司に言われなかったと思います。
OODAにもPDCAにも共通して言える大事な事。
それは「修正の速さ」なのです。
PDCAもOODAも全く別物なのでどっちがいいとか比較する必
でも、大事なことは「修正」なくして「達成」はない、ということ
★Aamazon kindleにて電子書籍出版しました。『ワークもライフも欲張ればいい。』是非ご一読ください。
⇒https://clearkyoto.com/news/326/
★研修の学びを深く定着する『反転学習』の提供スタートしました。
⇒https://peraichi.com/landing_pages/view/flippedclass
★すき間時間に学べる動画コンテンツ「チームマネジメント」リリースしました!
⇒https://www.enfac.co.jp/archives/projects/team-management
★森川の志:
働く人全てが納得感を持って働ける社会を創ること。仕事で結果を出しライフも充実することで人生は豊かになります。
そのためにはまず組織のコアである課長(中間管理職)の皆さんが生き生きと働くことで、その良い影響力を組織全体に広めていきます。
「課長と組織を変える人材開発」。これが私のミッションです。
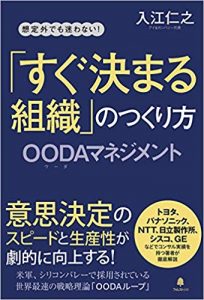
PDCAだと遅い!そんな話を聴いたことがあり購入。
一言でいうと「自律した組織にしよう」ということ。
つまり、社員一人一人が自分で考え行動する。
組織のビジョン。個人の夢に向かって行動する。判断基準はビジョンに向かっているか?
顧客や社会に価値を提供できているか?
その観点で行動を律し無駄を省き、効果性の高い行動をする。
組織もそんな個人をサポートするため、ビジョンにそった評価を行い、無駄の削減に共に歩む。
ざっくりいうとそんな感じ。
PDCAが別に不足しているわけではないと思います。ただ、確かにPの前に私は正直Cから入るケースがほとんど。
逆にC(現状把握)しないとPはできない。
そして効果的なC(振り返り)のためには目標やビジョンに対比して振り返らないと、やったかやってないかの振り返りになってしまう。
そして何より数値目標は色気がない。
数字をクリアすることが目的ではなくて、ビジョンや夢、世の中にどんなインパクトを与えたいか?がPの根源。数字はそれを表現するためのツールにすぎない。
たしかにPDCAでPを創るときは定量的にした方がいいのだが、同時に「ワクワクするゴールイメージ」を創らないと仕事が面白くなくなってしまう。
普段私が研修で話している事がOODAループ、という形で解説されています。
ただ、本書のいいところはOODAループの方法論にとどまらず、人事評価の仕組みや人材育成の仕組みにまで及んでいるところ。
つまり、マネジメントシステムをちゃんとしないと社員は効果的な行動がとれなくなってしまう。
つまり、個々の方法論ではなく、組織としてどう取り組むか?
その全体像が示されている。
そういった意味ではマネジメントに関わる人すべてにおススメできる本です。
冒頭のビジョンの共有。
個々のビジョンを明文化。
これだけでも効果大です。

