
課長と組織が変化する研修講師、clear kyotoの森川です。
日曜日は某組織の採用支援の仕事でした。
ここでは面接官として面接しながら、面接の進め方を担当者の方に学んでいただき、いずれ私なしで出来るようになってもらう。そんな仕事です。
ただ、時間の制約条件が結構きつく、結果グループ面接になってしまっているので、応募者一人に使える時間が短い。その中で採否を決めるのは中々難しい。
なので、こちらではグループ面接の後にグループディスカッションもしてもらい、最終的にその両方ですり合わせ会議を行い採否を決めています。
日曜日に改めて思ったこと。それは「対話の重要性」でした。
前述のとおりグループ面接なので、限られた時間で得られる情報量には限りがあります。
そしてこれ、応募者にとっても一緒なんです。
こちらの熱意や期待している事などを応募者もキャッチすることができない。
つまり相互理解の場になっていない、と言うことです。
そうなると何が起きるのか?
「よくわからないからやめておこう」となるんですね。これ、双方。
組織側も応募者側も。
ミスマッチになっているかどうかはこれまだ分かりません。
でも、組織側からすると確信をもって採用できない。
応募者側からすると自信をもって「ここに行きたい」と言えない。
組織側の想いや期待も伝わらないから、動機づけもできない。
と言うことです。
(なお、こちらの組織はこのことは百も承知ですが、時間の制約条件を会場できないため、今はやむなくこうなっています。ちなみに、採用活動のコミュニケーション設計については色々とありますが、それは次の機会に。)
そしてこれ、採用面接に限らず、上司部下の間でも普段から起きていませんか?ということ。
つまり、お互いを理解する場がありますか?
「わかっているはず」、というのは分かっているうちには入りません。
「仕事さえちゃんとやってくれていればいい」という人もいますが、その「ちゃんと」ってお互い理解できていますか?
それがないからお互いストレスが溜まっているのではないでしょうか?
同じ職場の人間といえど、赤の他人。
価値観が同じなんてことはないし、共通認識を持ち続けているなんてこともまずない。
だって、人間は感情で動く生き物だから、正論の前に感情が入ってきて、どう感じるかも変わるからです。
だから、「どう思う?」という確認の時間がないとまずいわけです。
最近はやりの1ON1。上司と部下が1対1で定期的に対話の時間を持つこと、です。
この効果について私は疑念があるわけではありませんし、むしろおススメです。
でも、効果的に行わないとこれも逆効果。
振り返りの場と言うと聞こえは良いのですが、振り返りと称して上司が詰める場になってませんか?
「今日どうだった。うんうん。え、それもできてへんの?なんで?何があったの?何故出来てないの?何故・・・?」
はい。何故が繰り返されるとただ詰めているだけになり、部下は思考停止します。
私の昔の上司は毎晩電話をしてくれてレビューしてくれるのですが、毎晩こんな風に詰められるので、辛さ以外何物でもありませんでした。(しかも当時の私はレビューの目的もちゃんと理解していなかったので、なおさら)
理由を聞くのが悪いわけではありません。
でも、相手が話やすいように聞かないといけない。
例えば、「そっか、それできなかったんだ。何が原因だったと思う?(ここで相手に考えさせる「間」をきちんと持つ)」
など。
1ON1の時、しゃべるボリュームは部下:上司=7:3くらいです。
部下にしゃべらせて部下自身に振り返りをさせ、部下自身が次のアクションを自分で選択する。
勿論それについて上司の意見も伝える。
でも、しゃべるメインは部下です。
コミュニケーションをとる=しゃべらなきゃ。
と思っている方は少なくありませんが、そうではありません。
コミュニケーションをとる=話をとにかく聴くこと、です。
相互理解ですからお互いの想いを理解する。
でも、まずは「聴く」から始めないと相手にこっちの想いは理解してもらえません。
だって、信頼関係の原則は
「理解してから理解される」
だからです。
でも、こういった場が定期的に持たれていると関係性が向上し、働きやすい職場環境となっていくのです。
******************************************
森川 宗貴(もりかわ むねたか)
clear kyoto合同会社 代表
(社)日本スケジューリング協会 専務理事
******************************************
★森川の「志」
clearkyoto合同会社では「課長と組織を変える研修」を企画提案しています。
組織のコアである課長のコミュニケーション力が変われば組織風土が変わり業績が変わるのです。
ここに徹底的にこだわり、働く人皆が「納得感」を持って働ける世の中を創っていきます。
オンラインもオフラインも提供しています。
https://clearkyoto.com/service_planning
★森川のもう一つの「志」
2020年より研修事業と併せて「コーチング」の提供をがっつり開始しました。
当社の理念は、
「働く人の”こう生きたい”を応援する」。
1人1人が公私ともにどんな生き方を実現したいのか?その理想の姿を言語化し、その実現に向けてどう変化し動くのか?
「人生におけるミッションとは作るものではない。発見するものである。」とビクターフランクルは言っています。
どう生きたいかは自身の内側にしかありません。それを発見し、イキイキ生きる支援をしています。
そんなイキイキ生きる人を増やしていく事が私のミッションでもあるのです。
https://clearkyoto.com/service_coaching
★「人間関係が楽になる」DiSCを使ったオンラインコーチングセッション。人とのかかわり方を科学的に、効果性を高める支援をしています。(個別のセッションも企業研修も対応可能です)
https://clearkyoto.com/service_disc
★現代のチームマネジメントのスキルが
すきま時間でスマホで学習できる全58本の動画を使った反転学習はこちら。
https://clearkyoto.com/service_inversion
★電子書籍『ワークもライフも欲張ればいい。』購入はこちらから。⇒https://clearkyoto.com/news/326/
★このメルマガは以前森川と何らかの形で名刺交換をさせていただいた方に送信しています。ご無沙汰の方もおられると思いますが、是非この機会に再度ご縁を繋げられたらと思っております。

課長と組織が変化する研修講師、clear kyotoの森川です。
コロナ禍ですっかりおなじみになったリモートワーク。
でも、一方で「リモハラ(リモートハラスメント)」という新しいハラスメントを生み出してしまいました。
メディアでも色々騒がれていますが、一応説明すると、リモハラとは、リモート会議や在宅勤務中に起こってしまうハラスメント。
セクハラ要素もパワハラ要素も含まれています。
例えば・・・
・恐ろしいこまめな進捗確認。
・そのタイミングでつながっていなかったら「さぼるな」と罵倒する。
・管理じゃなくて監視している感じ。分単位での報告を求められる。
・私服の部下に対していらん事言う。
・プライベートに土足で入り込む。「奥さんいるんだろ。見せろよ。」的な。
まあ、正直ショーもないことばかりですが、実際怒っている事なので看過できません。
そんな記事を見ながら思ったことは、もしかしてこの管理職の人達は「管理」という事そのものを勘違いしているのではないか?と言うことです。
実は少し前からも気になってました。
色々な会社の管理職研修に登壇していると、管理=現状把握、という理解をしている人が多い。
つまり、今どうなっているの?を事細かに知ろうとする。
うん。
別に間違いではありません。
でも、これだけだと足りません。
管理とは「現状を把握したうえで、良い方向に変化するように働きかけること」です。
だって、そうですよね。チームの目標達成が管理職のミッションです。
であれば、現状を把握するだけじゃなく、良い結果につながるように部下を支援すること。
当たり前と言えば当たり前なんです。
これはマネジメントだけではなく、「〇〇管理」という言葉に関しては全て同じです。
業務管理。時間管理。人員管理。備品管理。施設管理。。。沢山ありますよね。
じゃあ、リモハラはなぜ起こったのか?
マネジメントの前提が変わったことによる環境の変化に対応できていないことだと思います。
以前のようにみんなが会社にいれば、顔見れるし、空気も感じられるから、なんやかんやで適切なかかわり方が出来ていたのでは、と思います。
周りも空気を読んで上司を支えようとする。
そんな中でチームワークのようなものも生まれていたのではないでしょうか?
でも、リモートになったとたん何が変わったか。
目の前に部下がいない!!
顔も見れない。表情も分からない。何も伝わってこない。
つまり、ノンバーバルのコミュニケーションが皆無になったことにより、圧倒的に情報不足になりました。
そして不安になる。皆ちゃんと仕事しているのか?さぼっていないか?
そんな猜疑心でいっぱいになりました。
で、管理、というよりも監視に走ってしまった。性悪説になってしまったんですよね。
でも、リモートワークになるということは、仕事とプライベートの境界線があいまいになる、と言うことです。
となると、仕事中にご飯も作るし、子供の世話もするし、宅配も取るし、洗濯もするでしょう。
つまり、働くと生活するがごちゃ混ぜになる、と言う事なのです。
なのに、会社にいるのと同じ動きを求めるのは正直ナンセンスなんですよね。
むしろ、そんな環境の中部下が成果を出すためにどんな支援ができるのか?をゼロベースで見直さないといけない。
なのに、従来の管理を持ち込んだから、現状把握すらうまくいかなくなり、結果監視に走ってしまったのだと思います。
リモートが当たり前に本当になるのであれば、まず労働時間ではなく成果物で評価するようにしないと破綻します。
監視を続けると関係性が破綻するからです。そして意味がない。
コミュニケーションの取り方もお互い配慮したうえで効果的なコミュニケーションをとらないといけません。
例えば、日次レビューの時間は最初から決めておく。
時間中に家事などで離れることは関与しない。(結果さえ出ていればよい)
でも、いつでも相談の門戸は開いておく。
進捗確認するのであれば、そのタイミングをあらかじめ両者で決めておく。
離れている分、しっかりとお互いに合意形成しないと、ストレスがたまるだけだと思います。
そしてもちろんこれは部下サイドも成果を出すために上司とどう付き合うかを考えないといけません。
そういった意味では、どんな関わり方をしていくのかを一緒に模索するのがいいでしょう。
模索の過程できっと益々仲良くなれますよ!
******************************************
森川 宗貴(もりかわ むねたか)
clear kyoto合同会社 代表
(社)日本スケジューリング協会 専務理事
******************************************
★森川の「志」
clearkyoto合同会社では「課長と組織を変える研修」を企画提案しています。
組織のコアである課長のコミュニケーション力が変われば組織風土が変わり業績が変わるのです。
ここに徹底的にこだわり、働く人皆が「納得感」を持って働ける世の中を創っていきます。
オンラインもオフラインも提供しています。
https://clearkyoto.com/service_planning
★森川のもう一つの「志」
2020年より研修事業と併せて「コーチング」の提供をがっつり開始しました。
当社の理念は、
「働く人の”こう生きたい”を応援する」。
1人1人が公私ともにどんな生き方を実現したいのか?その理想の姿を言語化し、その実現に向けてどう変化し動くのか?
「人生におけるミッションとは作るものではない。発見するものである。」とビクターフランクルは言っています。
どう生きたいかは自身の内側にしかありません。それを発見し、イキイキ生きる支援をしています。
そんなイキイキ生きる人を増やしていく事が私のミッションでもあるのです。
https://clearkyoto.com/service_coaching
★「人間関係が楽になる」DiSCを使ったオンラインコーチングセッション。人とのかかわり方を科学的に、効果性を高める支援をしています。(個別のセッションも企業研修も対応可能です)
https://clearkyoto.com/service_disc
★現代のチームマネジメントのスキルが
すきま時間でスマホで学習できる全58本の動画を使った反転学習はこちら。
https://clearkyoto.com/service_inversion
★電子書籍『ワークもライフも欲張ればいい。』購入はこちらから。⇒https://clearkyoto.com/news/326/
★このメルマガは以前森川と何らかの形で名刺交換をさせていただいた方に送信しています。ご無沙汰の方もおられると思いますが、是非この機会に再度ご縁を繋げられたらと思っております。
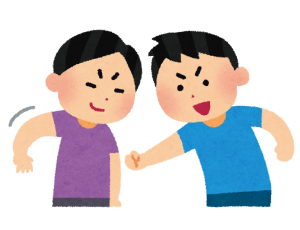
昨日登壇した、部下との面談力強化研修より。
部下との対話の効果的な進め方や話の聴き方、伝え方についての研修でした。
参加者のほとんどが毎月面談されているとのことなので面談慣れされている方が殆どだったのですが、ロープレ後の感想を聞いていると、
「どう伝えていいか考えすぎてなんか上滑りだった」という方が何人かおられました。
何故上滑りしたか?
それは、「話すことに集中してしまったから」、なんです。つまり、自分に焦点を当ててしまった。
面談ですから勿論「伝える」は大事です。
でも、その前にしなければいけないことは「聴く事」に集中すること。
信頼関係構築のためにも、まず聴く、はとても大事です。(第5の習慣、ですね)
そして何よりも、相手が話したいことをキャッチしてから伝えないと、かみ合わなくなるからです。
相手が言いたいことを聞く前に自分の話をしてしまったら、そりゃあかみ合わなくなる可能性大。
だって「対話」ですから。
伝えないといけないことがあると、そこに気持ちがいってしまう。
そんな時こそ、先に聴く。聴いた後に伝える。
後出しじゃんけんしましょう、ということです。

