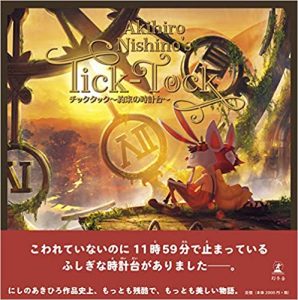
戦争を思い起こさせるような話の流れだな、と。
チックタックという時計台守とニーナという恋人(?)の物語なのだが、途中で「火の鳥」という火の雨が町を襲い町中焼けてしまう。そのタイミングで二人は離れてしまう。
失望の中チックタックはニーナが死んだことを認められない。(死体もでてきていない)
ずっと信じ続けていて結果、最後再会できるのだが、やさぐれながらも信じているチックタックがいじらしい。
愛ってそう簡単に割り切れるものじゃないんだな、と思うし、戦時中はこんな風に生き別れになるケースが沢山あったはず。
再会できなかったケースの方が圧倒的に多い。
無慈悲な戦争。無慈悲な暴力。テロ。
改めて嫌だし、でも、人間の気持ちはそんなことでは折れたりはしない、というメッセージにも感じる。
「夜と霧」のフランクルも、過酷な状況の中でも自分の意志は他人にコントロールできない、と言っている。
常に自分がどう在りたいか、が大事だし、目に見えない圧力や目に見える力に、心だけは折られたくないな、と改めて思う。希望を忘れなければ、やさぐれたとしてもなんとかなる。(はず)
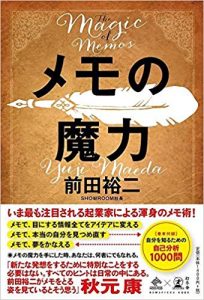
ニシノアキヒロさん推薦で購入しましたが、確かに面白い。
勿論メモの取り方がどんな効果があるか、について書かれていますが、本質は生き方や考え方ん本。
メモ、という切り口でここまで生き様を語れるのは、メモを真剣に、狂ったように取り、一生懸命生きてこられたからだと思う。それくらい感情が伝わってきて揺さぶられます。
HOW TOも内容には入っていますが、あくまでそれは手段と思えるくらい濃い内容です。
本書でも取り上げている「ファクト」⇒「抽象化」⇒「転用」という思考のプロセスは仕事をしていくときに差がつくポイントです。
ファクトは結構みんなやっている。だって出来事や言われたことをメモすればいい。
これをしないとコミュニケーションは始まらない。出来事や物事を知ろうとする、伝えようとすることです。
この先が問題。「抽象化」。
簡単に言えば具体的な物事に見出し(タイトル)を付けること。
「つまり、こういうこと」みたいな。まとめなおすような感じ。
抽象化するときは、WHAT、HOW,WHYの視点で考え直すと、次の転用に向かいやすい。特に、HOWとWHY。
これって、そうやってこうなったのか?というHOW目線で考えてみると気付きがある。
これって、なんでこうなったんだろう?という、WHY目線で考えてみると別の気付きがある。
思考を深めなおすプロセスともいえる。
要するに、メモを取りながら思考を整理し、深め、次のアイディアへの転用を考えていく。
彼にとってはメモが思考のプロセスそのものになっている。
そして何がいいって、それらが全て可視化されている事。
見返すことができる、という大きな利点。
あとは、言葉にすることのエネルギー。
言霊とか言いますが、言葉の達成予言力。私も研修でいつもお伝えしています。
言葉にして発するとそれが実現しやすい。
勿論ネガティブワードはネガティブな結果を引き起こす。
逆に「こうなりたい」とかは言葉にするべき。
流れ星にお願いしても別に流れ星が願いをかなえてくれるわけではなくて、強く念じるから自分で実現しているのだと思う。
私が講師になったきっかけは、28歳の時に受講した「7つの習慣研修」でした。
素晴らしい研修で感動したのですが、受講後同僚の臼井さんが「ねえ、もりもり。俺さ、いつかこの講座自分でやりたい!」といったのを聞いて「確かに。俺もそう思う」と意気投合したことを覚えています。
それから数年後。転職して人事の仕事をしている時に、一緒に働いていた山田君(できる男なのでひそかに尊敬していました)に「僕はね、森川さん絶対に研修講師がに向いてますよ。人事じゃなくて。」と言われました。
その2つがずっと頭に残っていて、人事時代に7つの習慣研修は講師の資格を取り社内で展開するようになり、その後講師として独立しました。(山田君はその時はもういませんでしたが)
二人にとっては軽く言った言葉かもしれませんが、私の中にはそれらがずっと残っていて、結局自分の生き方となりました。
それはずっと想っていたからです。
つまり本書は言葉にすることでエネルギーを強力にし、自分と約束し自分とアポを取り、人生を豊かにする。
難しいことは書いてません。(いや、ちょっとあるかも)
でも、メモという言葉の力で自分で人生を創っていこう。そんな主体的なメッセージをバチクソ受け取りました。
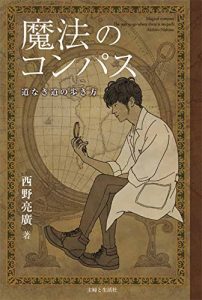
ご存知、お笑い芸人キングコングの西野さん。
私の後輩が彼のスタッフをしていることもあり、妙な親近感があるので必然的に事前期待高いまま読みましたがその期待を裏切らない面白さ。
実体験に基づいた言葉が沢山紹介されいているのだが、体験に基づいているので伝わってくる。
何かを伝えるときはそういった客観的な出来事(経験)を絡めて伝えることで、伝わってくる。
そして何より感心したのは、彼はいつも「問い」を持ちながら物事を見ている。
思考停止になることがないのはそのせい。
「どうしてこうなっているのか?」「どうやったら面白くなるのか?」など。
彼自身のユニークな才能も勿論あるとは思うが、それでも私たちが日常スルーしている事柄にまで問いをもっている。
箱根駅伝のランナーの速さが伝わらない。どうしたらいいか?とか思ったことありませんし。
そして何より素敵なのは失敗を失敗と認識していない。次へのステップと本気で思っている。
「失敗を存在させているのは、いつだって自分自身だ。
たしかに、どうにもならないことが世の中にはあるけれど、大丈夫。
大体のことはどうにかなる。」
沢山のトライを繰り返し沢山の失敗をしてきた彼だからこその言葉。
そう思えるくらい手数を出すって大事なんだと思う。
大丈夫。
死ぬわけちゃうし。

