【読了】ビジュアルで分かる日本
2025.04.01
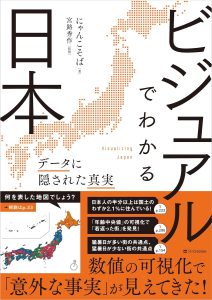
その名の通り、様々なデータで日本を読み解こう、という本書。
数字を見るのが嫌いじゃない人なら面白い。
改めて私たちはイメージで物事を見てしまっているよね、とも感じたりもします。
色々な数字の切り口が紹介されているのでそれだけでも興味深いのですが、一番なるほど、と思ったのが「コンビニと郵便局の立地差から見える企業の倫理」。
大手6社のコンビニは現在5万6千店。郵便局は2万4千局。
どちらもそれなりの街に行けば必ず出会う施設。ただ、コンビニのほうが3万も多いのは意外。
ただ、それを分布、というか所在地で見てみると大分差がある。
コンビニは都市部に集中し、漁村や離村、島などにはあまりない。
一方で郵便局は都市部とか農村関係なく均一に存在している。
それは郵便局は郵政民営化法などによって、全国均一にサービスを提供しないといけない、みたいな縛りがある。
つまり、インフラ、としての役割がある。
コンビニは勿論民間企業なので採算が取れないエリアには出店しない。
私はロードバイクで地方の町を走ることが結構多いのですが、地方に行けば行くほどコンビニに出会えない。
ちょっと前に夏場にタンゴイチ(丹後半島一周)しに行ったのですが、手持ちのドリンクが切れ、補給したいのにコンビニが出てこない。自販機もない。遭遇するのは郵便局ばかり。(あと、農協)
本当に水分切れぎりぎりのところで自販機を見つけ一息ついたのですが、その時一緒に走っていた友人と「郵便局、すげーな」と言っていたことを思い出します。
でも、郵便局も民営化しているので赤字続きでは持たない。でも、誰も郵便を出さない。そりゃあ、じり貧です。
なので、きっとこれからは農村のプラットフォームの役割みたいなことを求められるんだろうな、と。
郵便と預金と振込だけの機能にして(金融商品も売らなくていいし)、相手スペースで移動コンビニを誘致するとかすればもっと喜ばれそう。
でも、法律にがんじがらめなので、「そんなんとっくに考えたわ」と特定郵便局の局長をしている友人の顔が浮かびました。

